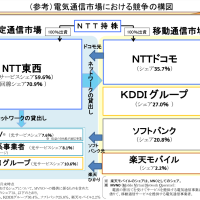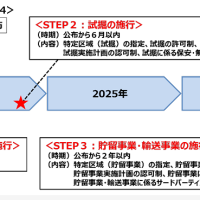サステナビリティ
サステナビリティ SH5222 環境省、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」を公表 宮川賢司/香川遼太郎(2024/12/02)
環境省は、2024年11月8日、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」および「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」(以下、併せて「本ガイドライン」と総称する。)を公表した[1][2]。
本稿では、本ガイドラインについて概説する。